
meet up Lab特別編では、「そもそも“ワーク”ってなに 好きなことしちゃダメですか?」をテーマに、このエリアで既存の枠組みに縛られない三人の女性――高林愛佳さん、関口裕子さん 、木元梨枝さん――をゲストに招き、田子直美をモデレーターに座談会を開催しました。
高林愛佳さんは、 自然食品と量り売り店「イツトクル」をオープンしました。学校に馴染めず不登校を経験。その後、日本各地やドイツを旅し、環境や食文化に触れて価値観が変化。結婚・出産後、無農薬の畑や米作りを始め、環境に負荷をかけない暮らしを実践しています。
関口裕子さんは、セレクトショップ「MMF→」を開店しました。幼少期から自由奔放で、学校のルールに縛られることが嫌でした。30歳のとき夫婦でセルフビルドで家を建て、40歳でショップを開業。自由を最優先に生きてきました。
木元梨枝さんは、幼少期から居場所のなさを感じ、心の病に苦しんだ時期もありました。2009年にコンテンポラリーダンスと出会い、芸術活動を通じて回復。現在は居場所づくりの活動を続けています。
彼女たちの生き方と、「こうあるべきから抜け出すこと」「暮らしを自分でつくること」について伺いました。
*本レポートはゲストのトークを中心にまとめました。
[目次]
・「みんなと同じ」から自由になる―環境と共に生きる暮らし(高林愛佳さん)
・「自由」を手放さずに生きる―セルフビルドとセレクトショップ(関口裕子さん)
・居場所を探し続けて―芸術が照らしてくれた生きる場所(木元梨枝さん)
・「こうあるべきから抜け出した日」
・「暮らしを自分で作ること」
田子直美:こんにちは、meet up Labの企画兼コーディネーターの田子です。
今回は、meet up Lab特別編として、私がみなさんにご紹介したいなと思った3人の女性をお招きしました。 肩書きや経歴でなく、彼女たちの生き方の魅力に気づいていただきたいと思っています。
はじめにお一人ずつ、お話を伺います。
「みんなと同じ」から自由になる――環境と共に生きる暮らし
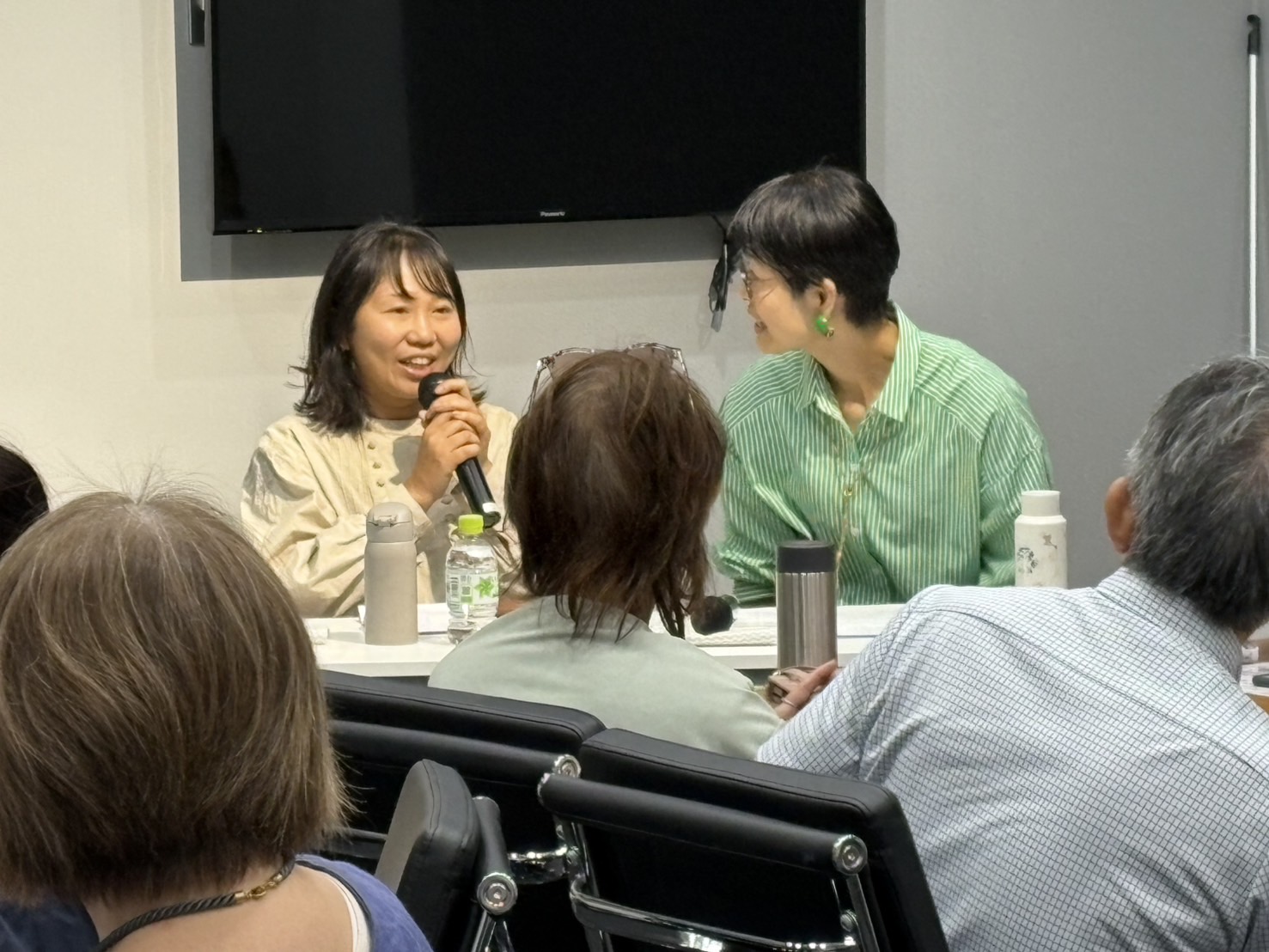
高林愛佳:「イツトクル」というお店を 5月27日にオープンしました高林愛佳です。
信濃市の宮川で生まれました。 いま42歳で8歳と5歳の子供が二人おります。
私は子どもの頃から大人を観察する性格で、学校生活には多くの疑問を抱いていました。行きたい時だけ学校に通い、勉強は嫌いではなかったものの、中学に入るとほとんど行かなくなりました。「みんなと同じにしなければならない」という空気がつらかったのだと思います。
15歳のとき両親が離婚し、母は心の病を抱え入院生活、祖父はアルコール依存、小学生の妹も問題を抱えていて、20歳までは日々を生きることに必死でした。その後母の体調も安定し、家を出て羽ばたける!という気持ちになって、日本各地を旅しながら暮らしました。京都ではシェアハウスで数年を過ごし、多くを学びました。
26歳で長野に戻り介護士として働き、高齢者の方々と接する中で「人生を楽しく生きなきゃ」という気持ちになりました。その後ドイツに渡り、ワーキングホリデーで一年間ヨーロッパを巡りました。環境への取り組みや食文化の違いに大きな衝撃を受けました。当時は自分一人の生活でしたから「いつ死んでもいい」と思うほど刹那的でした。
ドイツから帰国するときは日本社会に戻る不安があり、シンガポールやアジアを旅しながら「物に恵まれることが本当に幸せなのか」と考えました。33歳で帰国し再び旅を計画していたのですが、現在の夫と出会い、電撃的に結婚・出産。専業主婦として数年間育児に専念しました。やっぱり子どもが生まれてからですね、環境や食のことを考えるようになったのは。
40歳を前に「これからの生き方」を考え始め、無農薬の畑や田んぼを始めました。昨年からは米作りにも挑戦し、「環境に負荷をかけない暮らしを、自然のリズムに沿って実践したい」と考えるようになりました。今年、量り売りの店をオープンしましたが、それはゴールではなく、これからの一歩にすぎません。将来的には、自分の畑や手仕事から生まれるものを販売し、暮らしの一部として循環させていきたいと考えています。ドイツで学んだ「休暇を大切にする文化」も取り入れ、家族とゆっくり暮らしを楽しむことを大事にしたいと思っています。自分の実践が、誰かに「やってみよう」と思わせるきっかけになれば嬉しいです。
「自由」を手放さずに生きる――セルフビルドとセレクトショップ
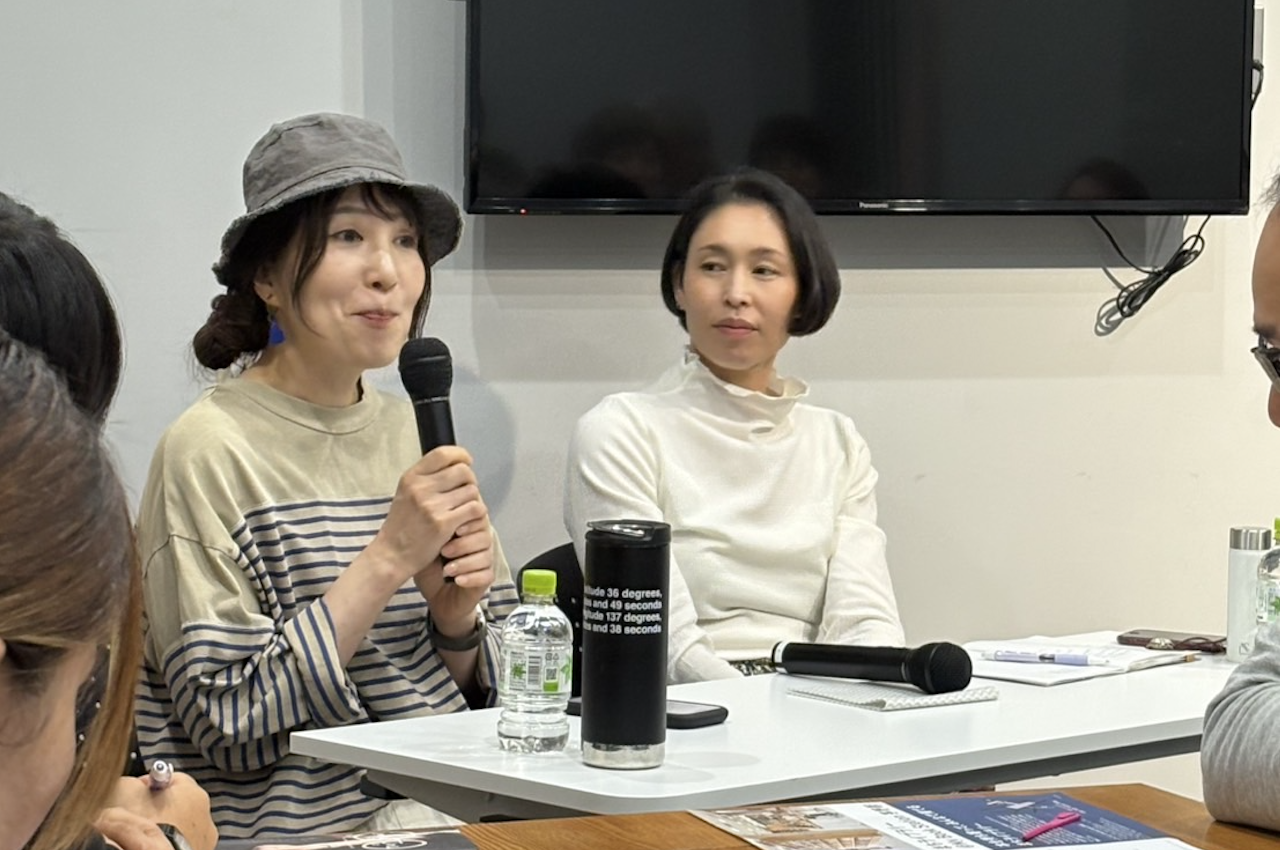
関口裕子:こんばんは、関口裕子です。
富士見町商店街で、天然素材中心の衣類を扱うセレクトショップ「MMF→」を営んでおります。
子供の頃は、おっとりしていましたが活発で、柔軟な性格ながら一度決めたら譲らない頑固な面もありました。高校生活はサボってばかり、気の向くままに過ごす日々でしが、アルバイトだけは真面目に通っていました。出席日数が足りず進級が危ぶまれましたが、心を入れ替え原宿のデザイン専門学校へ。またしても遊ぶ事に全力でを注ぎ、親に心配をかけました。
23歳で結婚。新婚旅行は意見が合わず、其々行きたい国へ1人旅をする自由な夫婦でした。就職経験はなく、バイト生活の日々でした。仕事だけは真面目なので社員のお誘いをいただくのですが、「社員になると自由がなくなる」と思っていたので、好きで初めた仕事も退職を繰り返しました。
28歳の頃長野県へ移住を決意。貯金はゼロでしたが、セルフビルドで建築したご夫婦の記事を見て「これだ!」と挑戦。融資に苦戦しながらも多くの人に支えられ完成しました。
その後も様々な仕事を経て、40歳を前に「自分で何かやろう」と決意。夫の「服屋でもやれば?」の一言をきっかけに「そうだね!」と開業。貯金は相変わらずゼロでした。学びと責任の日々の中、幸いにも多くのお客様に支えられ、今年で10年目を迎える事ができました。とても感謝しています。
10年走り続けて気づいたのは、「自由とは?」ということでした。仕事一筋のあまり、かつての自由が遠のいてしまったのです。私の今後の目標は再び自由を取り戻すことです。頑張ります!
居場所を探し続けて――芸術が照らしてくれた生きる場所

木元梨枝:初めまして、木元梨枝と申します。
子どもの頃から「自分はここに生まれてきたのが少し違うのではないか」という感覚があり、学校や友人、住む場所すべてを否定的に感じていました。自分が嫌いだし、友達も嫌いだし、住んでいる場所も嫌いだし、学校も嫌い…なので、勉強も取り組まず、小学校では算数のテストを裏返して寝てしまうなど、「ふてくされ症候群」だったんです。ずうっといじけていたので、早く自分に合う場所や仕事を見つけたいと思っていて、大人になるのを待ち望んでいました。
そんな自分を気にかけてくれる大人は多く、特に父の飲み仲間たちはよく面倒を見てくれました。魚の食べ方を教えてくれたり、体の弱さを心配して助言をくれたり。友達は少なく孤独でしたが、地元を離れたい一心で、高校は誰も知り合いのいない学校を選びました。勉強はできませんでしたが、家政科のクラスは衣食住を学ぶ場で楽しく、ようやく自分らしく過ごせたと感じました。
馬が好きだったこともあり、父の知人の紹介で、高校三年の夏には白樺湖ホープロッヂ乗馬牧場で住み込みアルバイトをしました。そこで現在の夫と出会い、23歳で結婚しました。しばらく牧場で働きましたが、ストレスから心の病を患い、幻聴に苦しみ入退院をくり返し、記憶が曖昧な時期を過ごしましたが、夫が支えてくれました。夫がいなかったらどうなっていただろうと思います。
転機は2009年だったと思います、市民館で見たコンテンポラリーダンスでした。人の体はこんなにも美しいんだ!と青天の霹靂というか強く感動して、心が動かされました。出演していたダンサーに「なんで踊っているんですか?」って聞いたんですね、そうしたら「なぜ踊らないのですか」と言われて、うわーっと興奮してすぐにもらったチラシにあったコンテンポラリーダンスのワークショップイベントの番号に電話しました。こんなふうにしてダンスのワークショップ公演に参加するうちに少しずつ心も快復してきました。ダンスはグレーだった暗い世界に、カッと光が差し込む感覚を得ました。
その後は自主公演をしたり、市民館のサポーターとして舞台制作に関わったりするようになりました。2012年に「藤浩志と部室をつくろう!」という美術館の企画に参加しました。当初活動が決まりませんでしたが、「つくった場所で起ることを日誌にしなさい。それがあなたの活動になるから」と助言され実行しました。この取り組みは「ひとともののであいどころ寄り部(ヨリブ)」と言って形を変えながら13年続いています。芸術を通し、すべてに否定的だったわたしはようやく生きる場所を見つけたのだと思います。
「こうあるべきから抜け出した日」

田子:ありがとうございました。今日は、二つのテーマを用意しました。一つは「こうあるべきから抜け出した日」、もう一つは「暮らしを自分で作ること」です。
はじめに、常識や普通とされることから外れた選択をしたときの葛藤や、周囲からの声にどう向き合ったのかを伺いたいと思います。
高林:私は小さい頃から「こうあるべき」に疑問を抱いていました。抜け出すというより、自分の直感を信じて選んできたと思います。最近ではお店を作る際、不安もあり銀行に相談しましたが、細かい計算のダメ出しを受けてとても落ち込みました。母に話すと「そんな人の言葉は聞かなくていい、第六感を信じて進みなさい」と言われ、決心しました。子どもも小さいので迷いましたが、今しかないと踏み切ることができたんです。
シンガポールに住んだとき、お金や物に囲まれることが本当に幸せなのかなあ?と感じました。帰国後に東京で無表情な人々を目にしたとき、カンボジアの人々が質素な暮らしの中でも笑って過ごしている姿を思い出して、幸せとは何なんだろうと強く感じました。
関口:私はこれまで、「こうあるべき」と疑問に思ったり、意識したことはありませんでした。そのため立ち止まることもなく、のほほんと生きてきたように思います。やると決めたことは、たとえ反対されたとしても、先ずは自分の気持ちを優先して挑戦してきました。これまで人間関係や仕事で大きなトラブルもなく過ごしてこられたのは、いつも温かく支えてくれた周囲の人たちのおかげだと感じています。自分の性格上あまり深く考え込むこともなく、何事もあっけらかんと通り抜けてきたように思います。
木元:私は高林さんと同じパターンかと思います。「こうあるべき」に対して常に疑問を抱いてきました。先生や大人の言葉をそのまま受け止めず、「?(はてな?)」で受け止めていました。留まって考えるタイプです。突破はせず、窮地を感じると現実逃避をして空を眺めていました。大人になってもその姿勢は変わらないと思います。
田子:違和感を突破するタイプと、壁にぶつかって自分が壊れないよう場所を変えて見たりして考えるタイプ、それぞれあるんだと感じました。
「暮らしを自分で作ること」

田子:では、「暮らしを自分で作る」について。お金のことも含めて、自分らしい暮らしをどう考えているか伺います。自分らしさとか、お金のこととか…。
高林:私は貯金をしたことがほとんどなく、やりたいことのために貯めては使う生活でした。結婚後も細々と貯めては家族で旅行を楽しんでいます。お金はあの世に持って行けないので、楽しいことに使いたいと考えています。お店はすごくいいご縁があってDIYすれば何とかなるという金額におさまりそうだったので、大きな融資は不要でした。必要なものは人から譲り受けたり自分で作ったりして、時間をかけて工夫しています。お金をかけずにやるというよりは、なるべく誰かが必要なくなったものを使ったり、作れそうならば自分で作るというスタイルがすごく楽しい。ちょっと時間がかかってもそういうふうに暮らしています。ダメだったら考えようという感じです。
関口:私は常にお金がない人でした。当然ながら使っていた訳ですが…。欲しいもの、やりたいこと、生活のために、働くことは必要不可欠でした。思い返せば高校を入学してから現在に至るまで、無職の期間は殆どありません。現在は.暮らしと仕事が一体化してしまい、運営のための融資も人生を進める手段としてネガティブに感じたことはありません。これも暮らしの延長線上にある”必要なこと”として捉えています。ただ仕事を抜きで考えると、暮らしに関しての自分らしさは欠落してしまったように思います。自由とは?とも繋がってきますが、一度頭の中をリセットしたいです。
木元:お二人はすごいなと思って聞いていました。私は病気で長く働けず、家計は夫に任せてきました。最近アルバイトをしましたが、体調との折り合いが難しく一年で辞めました。暮らしは夫の収入と、私の障害者年金で成り立っています。受給を決めたときは戸惑いましたが、実際には助けられています。そんなに裕福ではないけれど、二人で食べていけているというところです。逆に、私は、働きすぎると苦しかった嫌な時の感覚を思い出してしまうので、調整しながらやっています。今は自分のやりたいことを模索しているところです。だからお二人から聞きたい話がたくさんあります。
田子:ありがとうございました。
聞きたいことはたくさんありますが、時間の都合二より今日はこの辺で。ぜひみなさん、高林さん、関口さん、木元さんの活動を応援して、お店にも足を運んでみてください。
meet up Lab では、2〜3ヶ月に一度の開催で、東京ではできない暮らし方や働き方を、地元だからこそ実現できるという事例をご紹介しています。
例えば本日のお話にもありましたが、融資を受けずにお店を構えることは東京では難しいでしょう。でも、このエリアだからこそ可能であり、移住者にとっても夢のあることだと思います。そうした実例を積極的に発信していきたいと考えています。
今日は特別編で定員オーバーの満席でしたが、普段は、こじんまりとした雰囲気の中で、飲み物を片手にリラックスしながら語り合える場です。よろしければ次回もぜひご参加いただき、ゲストの方と直接つながっていただければと思います。きっと面白い出会いになるはずです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
了

| 【開催実績】 2025年9月19日(金) meet up Lab特別編「そもそも“ワーク”ってなに?好きなことしちゃダメですか」座談会 https://wly.jp/topics/20250919/ |